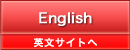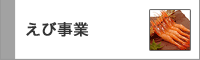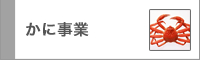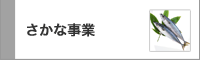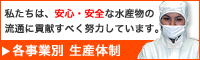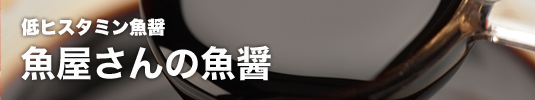
ヒスタミン規格は150ppm以下で世界基準に適合します。
「ヒスタミン」を大量に含む魚醤を食品の原材料に使用し、その食品を喫食した場合に「ヒスタミン食中毒」を起こすことがあります。当社の「魚屋さんの魚醤」は、鮮度抜群のアンチョビと天日塩のみを使用した魚醤で、世界基準のヒスタミン規格に適合しています。従って、「ヒスタミン食中毒」の心配がなく、食品の原材料として安心して使用することができます。
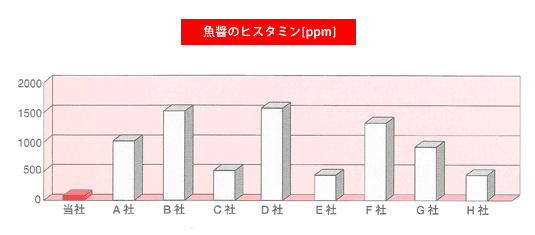
魚屋さんの魚醤の特徴
- 「魚屋さんの魚醤」を含む調味液の味がよくしみ込み、冷めても美味しさが長く持続します。豊富なアミノ酸とペプチドが、強いコク味(濃厚感)と複雑で伸びのある味を付与します。また、まろやかでバランスの良い味に仕上げます。
- 歩留りが向上し、加工時間が短縮されます。
- 冷凍耐性が向上し、解凍後のドリップが減少します。
- レトルト耐性が向上し、レトルト時の硬化防止効果があります。
- 魚臭、レトルト臭や水産練り製品に使用する植物たんぱく質の臭いマスキング効果があり風味を向上させます。
- 味の幅が広がって、呈味がアップします。
- 塩カドがとれて味がまろやかになります。
- 「リン酸塩」や「発色剤」の代替として「水産加工品」に「魚屋さんの魚醤」を使用すると、「リン酸塩」や「発色剤」と類似の効果が期待できます。
「低ヒスタミン魚醤」の対象水産加工品
フィーレ(てんぷら用、フライ用、煮魚用)、素干し品(するめ、干しだら、干し昆布)、煮干し品(煮干しいわし、干しあわび、干しえび)、塩干品(いわし干し、あじ干し、さば干し、さんま干し、開きだら)、魚類塩蔵品(サケ、マス類、サバ、イワシ類、ホッケ)、魚卵塩蔵品(すじこ、イクラ、数の子、たらこ、からすみ、キャビア、辛子明太子)、塩辛類(かつお塩辛、いか塩辛、うに塩辛)、海藻塩蔵品(生わかめ塩蔵品、ボイル塩蔵わかめ、塩蔵昆布)、冷薫品(サケ、マス類、ニシン、ブリ)、温薫品(サケ、マス類、ニシン、スルメイカ、タコ)、佃煮類(するめ、昆布)、調味乾燥品(イワシ類、サンマ、フグなどの味醂干し、さきいか)、調味魚介類(穴子、ブリ、サバ、ウナギ、さんま、シャケフレーク、イカ、タコ、エビ、カニグラタン、昆布まき)、調理酢漬け(しめサバ、マリネ)、板付きかまぼこ、ちくわ、湯煮製品(はんぺん、つみれ、鳴戸巻)、揚げ物(薩摩揚げ、加賀揚げ、野菜やイカを巻いたものなど種類も多い。)、カニ風味かまぼこ、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、缶詰品(ツナ缶、さんま蒲焼、サバ)、レトルト商品(いか飯、煮魚)、冷凍品(エビ、カニ棒肉)、味付け海苔、その他
「魚屋さんの魚醤」の品質規格の一例
| 原材料 | アンチョビ、天日塩 |
| 外観 | 褐色、澄明液体 |
| ヒスタミン含量 (ppm) | 150以下 |
| 殺菌の有無 | 火入殺菌済 |
| 全窒素 (g/100ml) | 2.5±0.2 |
| 食塩 (g/100ml) | 24±3 |
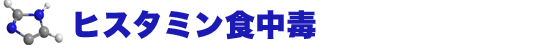
- 農水省は、平成22年8月2日の「リスク管理検討会」でヒスタミンを有害化学物質とした。
- 魚介類の鮮度が落ちると、魚介類に多く含まれるアミノ酸の一種の「ヒスチジン」をヒスタミン産生菌が、「ヒスタミン」という有害化学物質に変化させる。ヒスタミンは、熱を加えても分解されないため注意が必要である。
- 「ヒスタミン食中毒」とは、ヒスタミンを大量に含む魚介類を食べることにより、摂取直後から数時間の間に嘔吐、下痢、腹痛、頭痛、舌や顔面の腫れ、じんま疹、金属様の味、めまい、発熱といったアレルギー様の症状を起こす食中毒である。
- 日本では、魚介類の消費量が多いため、諸外国に比べてヒスタミン食中毒を起こす機会が多い。
- ヒスタミン食中毒は、幼児、保育園児、小学生や高齢者が発症しやすい。最近は、保育所、学校、病院が関係する給食施設でヒスタミン食中毒の集団発生が目立っている。
- 世界基準(コーデックス基準)では、冷凍を含む鮮魚は、ヒスタミン150ppm以下、魚醤などの魚の加工製品は、ヒスタミン200ppm以下と規定している。
- 水産加工工場でヒスタミン食中毒を予防するには、次の(a)~(c)の対策が必要である。
(a)ヒスタミンの少ない魚介類を仕入れる。
(b)加工工程でヒスタミンを増加させない。
(c)低ヒスタミン魚醤「魚屋さんの魚醤」を使用する。
「魚屋さんの魚醤」に関するお問い合せ
株式会社マール 〒104-0045
東京都中央区築地2-11-24 第29興和ビル別館7F
TEL:03-3524-0211 FAX:03-3524-0210
※お問い合せは、
当サイトメールフォームまたは、魚醤担当の横田(090-1127-7698)にお願いします。